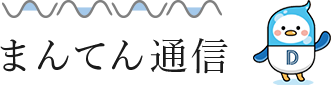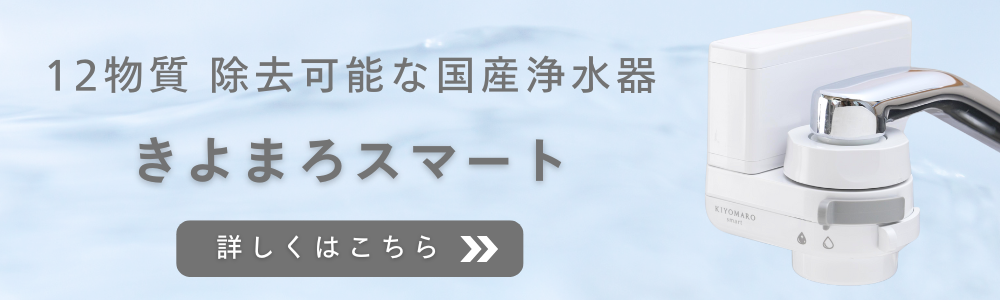暑い夏、熱中症対策で水分補給は欠かせません。しかし「水分を摂りすぎるとむくみが悪化する」と思い込んで、水分摂取を控えていませんか?実は、夏のむくみの真の原因は水分不足にあることが多いのです。正しい水分補給の知識を身につけて、健康で快適な夏を過ごしましょう。
意外な真実:水分不足がむくみを招く理由
水分補給量が少ないと、体が水を貯めこもうとしてむくみが生じることがあります。これは一見矛盾しているように感じますが、医学的にはしっかりとした根拠があります。
心臓から送り出される血液は体のすみずみまで行き渡り、しみ出した水分を老廃物などとともに吸収するのですが、水分不足になると血流が滞り、組織内に水分がとどまってしまうからです。
つまり、体内の水分循環が滞ることで、かえって余分な水分が蓄積されてしまうのです。夏は発汗により体内の水分が失われやすく、この現象がより起こりやすくなります。
夏場に知っておきたい適切な水分補給法
1日の水分摂取量の目安
厚生労働省によると、成人が1日に必要とする水分量は2.5Lです。ただし、この数値には食事から摂取する水分も含まれており、食事に含まれる水分量は、約600ml~1L前後です。
1日に必要な水分量の目安は、体重[kg]×30mlといわれています。体重50kgの場合は、1.5Lという計算になります。これは飲み物として摂取すべき量の目安となります。
効果的な水分補給のコツ
一度に多量の水分を摂取すると、内臓に負担がかかる上、血液中に余分な水分が溜まり、腎臓が弱っている方は特にむくみやすくなります。ゴクゴク一気飲みしてしまうくせのある方も、1回にコップ1杯分を、1日7~8回位に分けてこまめに飲むようにしましょう。
また、冷水でなく常温にすることで、胃への負担を軽減できます。暑い夏でも、極端に冷たい飲み物は体を冷やしすぎて血行を悪化させる可能性があるため注意が必要です。
むくみを悪化させる飲み物と食べ物
避けるべき飲み物
アルコールやカフェインには利尿作用があり、摂取した量以上の水分が身体から排出されます。水分補給どころか脱水状態を招きかねません。夏のビールやアイスコーヒーは美味しく感じますが、水分補給効果はあまり期待しない方が良いでしょう。
また糖質が多い飲み物ばかりだと、エネルギーとして消費しきれなかった糖質が水分と一緒に溜め込まれてしまいます。清涼飲料水やスポーツドリンクの飲みすぎにも注意しましょう。
塩分摂取の注意点
むくみの原因は、「水分」より「塩分」であることが圧倒的に多いもの。体内に塩分が多くなると、体は濃度を一定に保とうとして、水分をため込みやすくなり、むくみを悪化させてしまいます。
夏場は汗をかくため塩分補給も大切ですが、夏場とはいえ、塩分補給は通常通りの食事で十分。激しいスポーツや炎天下での肉体労働で汗を多量にかく方の場合は、おやつ代わりに塩飴をなめるなどの対策がおすすめです。
理想的な水分補給で夏を乗り切る
おすすめの飲み物
市販のミネラルウォーターや麦茶は、ノンカフェインでミネラルもバランス良く含むのでおすすめです。特に、溜まった毒素や水分を排出する効果のある、ミネラル(カリウム)を豊富に含んだ飲み物を選ぶことで、むくみの予防効果も期待できます。
生活習慣の改善
水分補給だけでなく、適度な運動や体を冷やしすぎない工夫も大切です。冷えにより血液の循環が悪くなると、むくみやすくなります。エアコンの効いた室内では、ひざ掛けや上着で体温調節を心がけましょう。
まとめ:正しい知識で快適な夏を
夏のむくみは水分の摂りすぎではなく、むしろ水分不足や不適切な水分補給が原因となることが多いのです。1日を通してこまめに適量の水分を摂取し、塩分や糖分の多い飲み物は控えめにすることで、熱中症予防とむくみ対策の両方を実現できます。正しい水分補給の知識を身につけて、健康で爽やかな夏をお過ごしください。
◎参考文献・出典