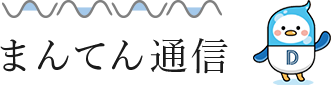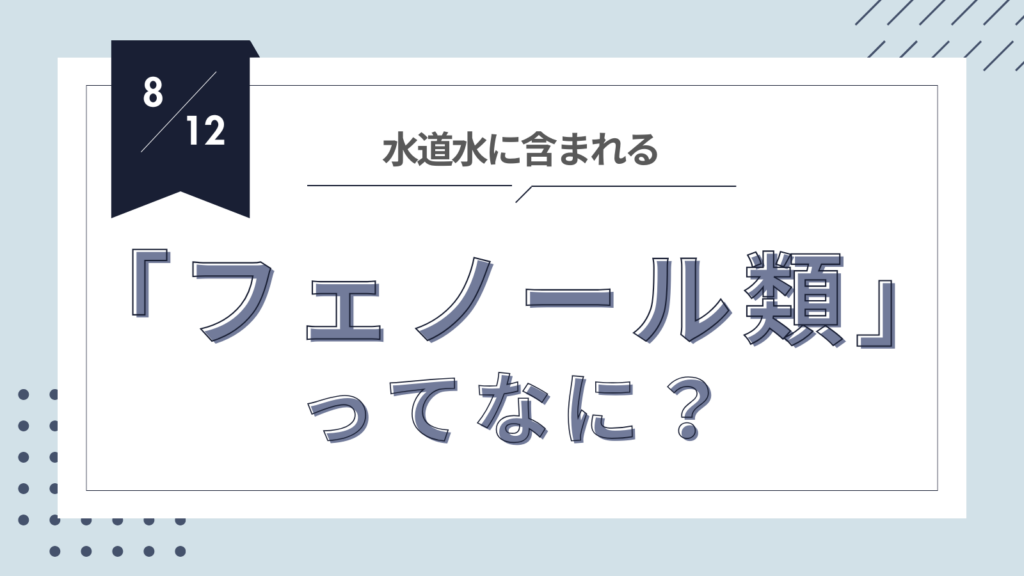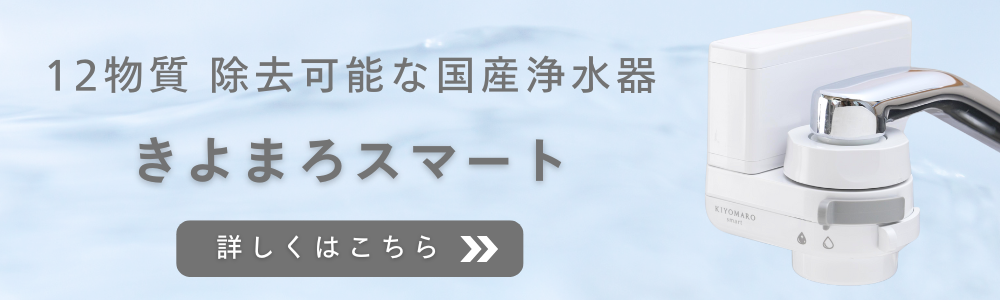水道水を飲んだ時、「なんか薬品っぽいにおいがする」と感じたことはないですか?実はそのにおいの原因はフェノール類かもしれません。あまり聞きなじみのない言葉ですが、水道水の味を損なう原因となっている物質とされています。この記事ではそんなフェノール類の特徴や人体への影響などを解説します。
フェノール類ってどんな物質?
フェノール類は、「ベンゼン」という環の形をした炭素の集まりに、水酸基(–OH)がついた化学物質です。代表的な物質としては「フェノール(C₆H₅OH)」があり、無色でツンとした独特の刺激臭を持ちます。
このフェノール類は、合成樹脂、医薬品、農薬、洗剤、染料などの工業製品の原料や中間体として広く使用されており、その製造や使用過程で排出される廃水に含まれることがあります。
フェノール類が水道水に入る理由
フェノール類は自然水中には含まれていません。また、水道水は厳重な浄水処理を経て供給されているため、有害物質が混入することはほとんどありません。しかし、以下のようなケースで水源にフェノール類が混入することがあります。
- 工場からの排水が不適切に処理されたまま河川に放出される
- 都市部などで生活排水に含まれるフェノール類が下水処理で除去されず流出する
- 廃棄物の不法投棄によって地表水や地下水が汚染される
このようにしてフェノール類が原水(川や湖、地下水など)に入り込んだ場合、浄水場での処理で完全に除去しきれないケースがまれに発生します。とくに塩素消毒を行った際、フェノール類と塩素が反応し、「クロロフェノール」という悪臭物質を生成することがあり、これが水の「薬品臭」や「消毒臭」として感知される原因となります。
フェノール類の水質基準は?健康への影響はある?
水質基準項目では、水道水のフェノール類について0.0005 mg/L(=0.5 µg/L)を上限とする水質基準を定めています。これは、においや味を通じて違和感が生じる前の段階で設定された、非常に厳しい基準です。
仮に基準値を超えた場合でも、直ちに健康被害が起きるわけではありませんが、長期的な影響や慢性的な曝露によるリスクを回避するために、定期的なモニタリングと対策が徹底されています。
フェノール類は高濃度で摂取した場合、中枢神経系、肝臓、腎臓などへの毒性が報告されており、労働環境などでは適切な管理が必要とされています。ただし、水道水に含まれる濃度はごく微量であり、適切に管理されていれば日常生活での健康影響はないと考えられます。
フェノール臭がする水への対処法
水道水から薬品のようなにおい、あるいはカビ臭に近い違和感を感じた場合、その原因のひとつとしてフェノール類の存在が考えられます。その際に取れる対策としては、以下のような方法があります。
1. 浄水器の使用
とくに活性炭を使用した浄水器は、フェノール類やクロロフェノールなどの有機化合物を吸着する効果があります。蛇口に取り付ける簡易タイプから据え置き型まで、家庭で手軽に導入できます。
2. 一度沸騰させて冷ます
臭気成分の一部は揮発性があるため、煮沸することでにおいが軽減される場合もあります。ただし、すべての成分を除去できるわけではなく、揮発しない成分は残るため、根本的な解決にはなりません。
3. 水道局に連絡して調査依頼
においが明らかに異常と感じられる場合は、地域の水道局に連絡し、水質調査を依頼するのも一つの手です。水源や浄水処理に問題がある可能性があるため、速やかな対応が求められます。
日常生活で気をつけたいポイント
水道水は毎日使用するものだからこそ、においや味の変化に気を配ることは大切です。以下のような変化が見られた場合は注意が必要です。
- においがいつもと違う(薬品臭、カビ臭、土臭など)
- お茶やコーヒーの味が変わったと感じる
- 食器やポットににおいが残る
こうした異変に気づいた際は、浄水器の導入や水の使用方法の見直しを検討するとともに、水道局からの情報にも目を通す習慣をつけておくと安心です。
フェノール類などの異臭対策には自衛手段も重要
日本の水道水は世界的にも高い安全性を誇っており、フェノール類をはじめとする有害物質の管理も徹底されています。しかし、自然災害や突発的な工場事故などで、想定外の化学物質が混入するリスクはゼロではありません。においに敏感な方や、乳幼児・高齢者のいる家庭では、浄水器の使用や情報収集を習慣化することで、より安心して水を利用することができます。
きよまろスマートはフェノール類を含む12物質除去可能な蛇口直結型浄水器です。
90%の蛇口に対応で取付も簡単なので、水道水の薬品臭やカビ臭にお悩みの方は検討してみてはいかがでしょうか。